新着記事
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
2025年 4月 3日 12:00
縮刷版購入者特典の通販新聞
全文記事検索サービス
年間購読のお申込み
人気記事ランキング
1
2025年 3月27日 12:00
2
2023年 8月24日 12:00
3
2023年 7月20日 12:00
4
2024年12月23日 12:00
5
2024年 9月19日 12:00
6
2025年 3月 6日 12:00
7
2025年 3月20日 12:00
8
2025年 3月27日 12:00
9
2025年 3月20日 12:00
10
2025年 3月27日 12:00
1
2025年 3月27日 12:00
2
2025年 3月27日 12:00
3
2025年 3月27日 12:00
4
2025年 3月27日 12:00
5
2023年 8月24日 12:00
6
2025年 3月27日 12:00
7
2025年 3月27日 12:00
8
2025年 3月27日 12:00
9
2025年 3月27日 12:00
10
2025年 3月27日 12:00
1
2025年 3月 6日 12:00
2
2023年 7月20日 12:00
3
2023年 8月24日 12:00
4
2025年 3月 6日 12:00
5
2025年 1月16日 12:00
6
2023年 7月 6日 12:00
7
2024年 9月19日 12:00
8
2025年 3月 6日 12:00
9
2025年 2月27日 12:00
10
2025年 3月13日 12:00


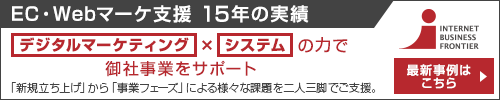








「ありがとうございます。DHCは、『利用している(利用したい)機能性食品メーカー』第1位に選ばれました」。8月16日以降、DHCの全面見開き広告を飾った清々しい文面とは対照的に、その背後ではある騒動が起こっていた。
問題となったのは、第1位の根拠として広告に引用された調査データ。中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局(以下、北陸支局)の補助金事業でジェック経営コンサルタントが行ったものだ。北陸支局は「不適切な内容が含まれる」と調査の公表を止め、広告に使わないよう要請したが、DHCは掲載を強行した(本紙1379号既報)。
◇
北陸支局とジェック社が問題視するのは、著作権法における引用の部分。支局では委託事業と異なり、補助金事業の場合、著作権は助成先の民間企業に帰属するとの見解を示す。まず、その観点から広告を検証したい。
この違いに北陸支局は「『補助を受けた』は正しいが、『主管した』は誤認を招く、『行った』は事実と異なる」とする。逆にDHCサイドから捉えれば、「行った」と表現できることが最も好ましいと考えることができる。複数紙を確認した限り、引用元に調査元のジェック社の記載は見当たらない。
言うに及ばず、通販会社にとって、広告クリエイティブは生命線だろう。文言、字体、ビジュアル...細部の違いが反応率を大きく変える。これに最も精通するのが通販事業者だ。また、著作権法でも「引用」には細心の注意を払う必要がある。
「推測の域を出ないが、入手しにくい地方紙は全般的に『行った』と書かれ、目に付く地元紙は『補助を受けた』となっている。何か意図があったのか」(北陸支局)。その疑問を紐解くカギは、DHCの創業来の歴史にある。
◇
1977年、当時「大学翻訳センター」の名で委託翻訳業を行っていたDHCは、大学で使う語学教科書や副読本の翻訳、いわゆる"虎の巻"を販売していた。だが、これが問題となる。著者や出版元に無断で翻訳し、学生に売りさばいたとして著作権法違反で東京地検に告訴されたのだ。
04年には日本画家、田中一村の映画化を巡り、"映画の中で作品を使えば著作権侵害"として、田中氏の遺族から作品の使用差し止めの仮処分を東京地裁に申し立てられ、09年にはクレンジングの特許を侵害したとしてファンケルがDHCを東京地裁に提訴。今年5月、DHCが敗訴した(上告中)。そして、今回の調査資料の無断使用だ。
いわばDHCにとって知財軽視は"お家芸"。これを研究し、他者の持つ知財をきわどいところでかわそうとしてきたスタンスが垣間見えるのだ。今回の広告も仮に消費者の受け取り方を意識し、許されるぎりぎりの範囲で意図的に広告文言に変化をつけたのであれば、それは虚飾に満ちた広告といえるだろう。法以前に企業倫理が問われる。
◇
北陸支局とジェック社は8月20日付けで、DHCに抗議書(ジェック社は「申入れ書」と説明)を送付。それぞれ「広告に不適当な表現があるため訂正記事の掲載(注・社告掲載など含む)と広告の掲載中止をお願いした」(北陸支局)、「調査データの無断使用による著作権の侵害で抗議した」(ジェック社)とする。
ジェック社では提訴に踏み切るかに「出方によるが、支局と相談しながら考えたい」。北陸支局も今後の対応を「回答を見て見極めたい」とする。
ただ、DHCの広告問題は3者間の問題で落ち着きそうもない。多くの同業他社の反発を招き、その余波は周辺企業にまで広がろうとしている。
(つづく)