.jpg)
前号に続き、アリババグループの伊勢公一氏に、中国におけるライブコマースの現状などを聞いた。
◇
――ライブコマースが企業にとって必要不可欠な取り組みとなっている。
「ライバーをキャスティングして、ライブコマースで知名度を上げていくブランドもあれば、自分たちでコツコツとライブコマースに取り組むブランドもある。自社の店舗からライブコマースを手がける割合は、全体の6割程度まで増えている。ベビー用の医療機器ブランド『ベビースマイル』を展開する、シースターの山藤清隆社長に話を聞いたところ、トップクラスのKOLから『ぜひ御社のベビー用歯ブラシを紹介させてほしい』と声がかかったそうで、こういったパターンもある。KOLは商品に関する知識があり、『かゆいところに手が届く』ような、すぐれた商品を消費者に紹介するのが、存在価値の一つだ。消費者の好みが多様化する中で、世界中のさまざまな商品に目を向けている。ライバー側も、メジャーな商品を紹介して、それにクーポンを付与するだけでは生き残るのが難しくなってきている」
――トップクラスのKOLに頼む場合のコストは、売り上げに見合うものなのか。
「トップのKOLに依頼した場合、効果はその場で商品が売れるというだけの一過性のものではない。自社商品へのリンクを通じて、店舗ページに訪問してもらえるわけだ。そこでフォロワーになってもらえれば、新製品情報やキャンペーン情報を届けることができるようになる。コンバージョン率を高めていくためには欠かせない取り組みなので、消費者と長期的にコミュニケーションを取るための投資と考えるべきだろう」
――自社でライブコマースを行うというのは、社員で配信するということか。
「昨年のダブルイレブンでいえば、自治体や企業のトップが自ら消費者に語りかけるというスタイルもかなりみられた。その流れで、ブランドが自分たちの言葉でしゃべるという取り組みも継続している。経営者や商品開発担当者がモノづくりの当事者として消費者とダイレクトにコミュニケーションを取ることは、自社の信頼性やロイヤリティーを上げることにつながる。また、OTC医薬品のように、カテゴリーによっては『正しい情報発信』へのこだわりから、自社での情報発信を重視するブランドもある」
――タオバオライブを通じた流通も伸びているのか。
「タオバオライブを通じた年間流通総額は4000億元(約6兆4800億円)を超えた。成長率でいえば、4~6月の流通総額は前年同期の2倍以上となっている。配信プラットフォームと購買プラットフォームが統一されており、出店者・消費者お互いにとって使いやすいのが強みだ」
――コロナ禍を受け、日本企業の越境ECへの意欲はどう変化したか。
「意欲は加速していると感じる。2019年には訪日外国人旅行者が3000万人を突破し、特に中国からの観光客は1000万人を超えるのではないかと言われていたわけだ。それが昨年3月以降はコロナ禍でほぼゼロとなった。日本企業はそれに変わる販売チャネルを模索しているわけで、当社のサービスであればTOF(中国向け海外直送サービス)の利用が広がっている。これまでは旗艦店スタイルしか打ち出していなかったものが、販売チャネルを増やしたことで、利用企業が広がっているわけだ」
――日本企業が越境ECを利用する場合の販売チャネルは。
「天猫国際に店舗を開く旗艦店スタイルだけではなく、TOFとTDI(代理販売モデル)がある。TDIについては、ある程度販売量が見込める商品を当社が大量に購入し、販売するというモデルだ。旗艦店から一歩進んだ形の取り組みとなる。逆にTOFは『旗艦店を出すのはハードルが高い』という企業に向けたチャネルで、テストマーケティングとして使ってもらいたい。コロナ禍による越境ECへの意欲増を受け、当社としても昨年下期からはTOFにフォーカスを当てている」
――TOFを利用する日本企業は中小が多いのか。
「大手企業がメイン以外のブランドのテストに使うケースもあるし、立ち上げたばかりの美容機器メーカーが試すこともあるので、かなり幅広い。色やサイズが豊富でSKUが多い商材の場合、膨大な在庫を中国に送るのはリスクが高い。そういう面では、国内で在庫管理ができるTOFは、SKUが多い商材がマッチしている。直送なので軽くて小さく、20~30代女性に向けた商品が向いているため、そういったブランドに出店してもらい、当社としても消費者とのマッチング精度を上げていきたい」
――消費者の需要を伝えるなど、コンサルティング的なことは行っているのか。
「幅広く商材を集めて消費者に買ってもらうのが一番重要だ。例えば、味の素が天猫国際に出店した際、想定外に売れたのが『塩』だった。塩分を50%カットした『やさしお』という商品で、日本では血圧を気にする高齢者を主なターゲットとしている。ところが、中国ではベビー向けに購入する消費者が多かった。メーカーも当社もこうした受け入れられ方は全く想定していなかったので、実際に売ってみないと分からない部分が大きい」(おわり)


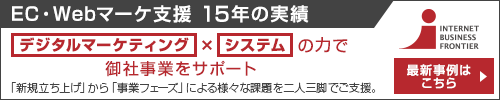








◇
――ライブコマースが企業にとって必要不可欠な取り組みとなっている。
「ライバーをキャスティングして、ライブコマースで知名度を上げていくブランドもあれば、自分たちでコツコツとライブコマースに取り組むブランドもある。自社の店舗からライブコマースを手がける割合は、全体の6割程度まで増えている。ベビー用の医療機器ブランド『ベビースマイル』を展開する、シースターの山藤清隆社長に話を聞いたところ、トップクラスのKOLから『ぜひ御社のベビー用歯ブラシを紹介させてほしい』と声がかかったそうで、こういったパターンもある。KOLは商品に関する知識があり、『かゆいところに手が届く』ような、すぐれた商品を消費者に紹介するのが、存在価値の一つだ。消費者の好みが多様化する中で、世界中のさまざまな商品に目を向けている。ライバー側も、メジャーな商品を紹介して、それにクーポンを付与するだけでは生き残るのが難しくなってきている」
――トップクラスのKOLに頼む場合のコストは、売り上げに見合うものなのか。
「トップのKOLに依頼した場合、効果はその場で商品が売れるというだけの一過性のものではない。自社商品へのリンクを通じて、店舗ページに訪問してもらえるわけだ。そこでフォロワーになってもらえれば、新製品情報やキャンペーン情報を届けることができるようになる。コンバージョン率を高めていくためには欠かせない取り組みなので、消費者と長期的にコミュニケーションを取るための投資と考えるべきだろう」
――自社でライブコマースを行うというのは、社員で配信するということか。
「昨年のダブルイレブンでいえば、自治体や企業のトップが自ら消費者に語りかけるというスタイルもかなりみられた。その流れで、ブランドが自分たちの言葉でしゃべるという取り組みも継続している。経営者や商品開発担当者がモノづくりの当事者として消費者とダイレクトにコミュニケーションを取ることは、自社の信頼性やロイヤリティーを上げることにつながる。また、OTC医薬品のように、カテゴリーによっては『正しい情報発信』へのこだわりから、自社での情報発信を重視するブランドもある」
――タオバオライブを通じた流通も伸びているのか。
「タオバオライブを通じた年間流通総額は4000億元(約6兆4800億円)を超えた。成長率でいえば、4~6月の流通総額は前年同期の2倍以上となっている。配信プラットフォームと購買プラットフォームが統一されており、出店者・消費者お互いにとって使いやすいのが強みだ」
――コロナ禍を受け、日本企業の越境ECへの意欲はどう変化したか。
「意欲は加速していると感じる。2019年には訪日外国人旅行者が3000万人を突破し、特に中国からの観光客は1000万人を超えるのではないかと言われていたわけだ。それが昨年3月以降はコロナ禍でほぼゼロとなった。日本企業はそれに変わる販売チャネルを模索しているわけで、当社のサービスであればTOF(中国向け海外直送サービス)の利用が広がっている。これまでは旗艦店スタイルしか打ち出していなかったものが、販売チャネルを増やしたことで、利用企業が広がっているわけだ」
――日本企業が越境ECを利用する場合の販売チャネルは。
「天猫国際に店舗を開く旗艦店スタイルだけではなく、TOFとTDI(代理販売モデル)がある。TDIについては、ある程度販売量が見込める商品を当社が大量に購入し、販売するというモデルだ。旗艦店から一歩進んだ形の取り組みとなる。逆にTOFは『旗艦店を出すのはハードルが高い』という企業に向けたチャネルで、テストマーケティングとして使ってもらいたい。コロナ禍による越境ECへの意欲増を受け、当社としても昨年下期からはTOFにフォーカスを当てている」
――TOFを利用する日本企業は中小が多いのか。
「大手企業がメイン以外のブランドのテストに使うケースもあるし、立ち上げたばかりの美容機器メーカーが試すこともあるので、かなり幅広い。色やサイズが豊富でSKUが多い商材の場合、膨大な在庫を中国に送るのはリスクが高い。そういう面では、国内で在庫管理ができるTOFは、SKUが多い商材がマッチしている。直送なので軽くて小さく、20~30代女性に向けた商品が向いているため、そういったブランドに出店してもらい、当社としても消費者とのマッチング精度を上げていきたい」
――消費者の需要を伝えるなど、コンサルティング的なことは行っているのか。
「幅広く商材を集めて消費者に買ってもらうのが一番重要だ。例えば、味の素が天猫国際に出店した際、想定外に売れたのが『塩』だった。塩分を50%カットした『やさしお』という商品で、日本では血圧を気にする高齢者を主なターゲットとしている。ところが、中国ではベビー向けに購入する消費者が多かった。メーカーも当社もこうした受け入れられ方は全く想定していなかったので、実際に売ってみないと分からない部分が大きい」(おわり)