メルカリが運営する、フリマアプリ「メルカリ」上のECプラットフォーム「メルカリShops」の流通額が急伸している。「初期費用・月額費用ゼロ」を武器に、出店するEC企業も急増。2025年12月期の流通額は3000億円を目指しているとの観測もある。新興仮想モールとして勢いを増す、メルカリShopsの「強み」と「弱み」は。

流通額ではアマゾンと楽天市場が2強、離された3位がヤフーショッピング。Qoo10とauPAYマーケットがこれに続く。近年、仮想モールを巡る構図は固定されていた。そこに殴り込みをかけたのが、これまでC2Cをメインとしてきたメルカリだ。流通額を大きく伸ばしており、Qoo10やauPAYマーケットに迫る勢いを見せている。
メルカリShopsは2021年のサービス開始当初、コロナ禍で苦しむ地域の生産者のための販路」という色合いが強く、クリエイターのハンドメイド作品や農家直送の野菜や果物、飲食店のグルメ、地方の特産品などの出品を想定していた。しかし、近年は機能的にも「仮想モール」へと近づくとともに、大手EC事業者も続々参入している。

カニなどを販売する「越前かに職人甲羅組」の伝食では、2022年10月にメルカリShopsに出店。担当する通信販売部通販運営企画課・福地志穂美課長代理は「『メルカリ』で何か売れると『売上金はどうしようか』となる。銀行口座に振り込むと手数料がかかってしまうわけで、甲羅組としてメルカリShopsに出店すれば、購入するというよりも、売上金と『交換』する需要が生まれるのではないかと考えた」と振り返る。
出店以降、売り上げは順調に推移。メルカリShopsの優秀店舗を表彰する「メルカリShopsアワード2024」において、総合3位を受賞した。福地氏は「他の仮想モールはリピーターが70%程度を占めることが多いが、メルカリShopsの場合は新規がほぼ半数を占めている」と説明。売上金を使う目的ということもあるのか、安い商品を探しているユーザーが多い傾向にあるという。
メルカリShopsアワード2024では甲羅組以外にも、アイリスプラザや「いわゆるソフトドリンクのお店」のナカヱなど、楽天市場などでおなじみのEC企業が受賞。大手家電量販店のエディオンなど、EC専業以外の大手企業も。流通額が伸びているだけに、今後は大手企業のメルカリShopsへの出店は増えるものとみられる。
検索広告を開始
メルカリShopsを統括する、江川嗣政執行役員は「3月に(『メルカリ』としての買い物イベントである)『超メルカリ市』を開催したこともあり、もう一段階成長した感がある。出店者数も流通総額も順調に成長しており、EC事業者からの期待も実感できている」と近況を語る。
具体的な出店者数については公表していないが、法人出店に関しては2桁増のペースを維持しているという。「楽天市場などで活躍している上位店も増えているが、リユース大手の出店も目立つ」(江川執行役員、以下同)。直近では、漫画古書店のまんだらけが出店した。
メルカリShopsの場合、初期費用と月額費用が無料で、売れた場合のみ10%を支払う仕組みのため、他社の仮想モールよりも割安感があるのが特徴。加えて「メルカリ」自体の集客力が大きな魅力となる。
営業部隊に関しては、出店者を獲得するチームと、楽天でいう「ECコンサルタント」の役割を持つチームの2つに分かれる。出店者を獲得するチームに関しては、決済サービス「メルペイ」や単発アルバイト仲介サービス「メルカリ ハロ」などと同時に営業をかけるケースも増えている。さらには、「メルカリ」への広告出稿を提案、「メルカリ」の集客力を実感してもらってから出店してもらうケースもあるという。
直近の大きなトピックスは、昨年末の検索連動型広告導入だ。江川執行役員は「広告に関しては、他の仮想モールと大きな差があった部分。競合との差を埋めていくためのスタートを切ることができた」と話す。
現在、3桁の店舗が検索連動型広告を使っている。現状については「使っている店舗が増えれば増えるほど、クリック単価は上がっていくわけだが、まだ思ったほど高くなっていない。逆に、利用企業からみれば費用対効果は良いのではないか」。
広告商品は、検索画面の上から4番目に表示される仕組みだ。「『メルカリ』は元来C2Cマーケットなので、C2Cの商品を探しに来るユーザーが多いという仮説を立てた。そのため、上段はC2C商品にした方がユーザーにとっては良いのではないかと判断した」ためだ。もちろん、出稿する企業にとっては、1番上に表示されると効果が高いのは間違いない。メルカリでは、ユーザーが検索した際に表示する商品のマッチング精度を高めることで対応したい考えだ。
また、アプリの検索画面において、メルカリShopsを利用している法人が出品する商品を、それと判別することはできない。これについて、江川執行役員は「法人出品者を特別に目立たせることは考えていないが、信頼のおけるセラーを大切にしていきたいとは思っている。過去の取引実績や販売のボリューム、顧客とのトラブルはないかといった点を考慮し、『安心・安全』な出品者については検索アルゴリズムにある程度反映させたい」と説明する。
「カゴ導入」課題
現状、大きな宿題となっているのは「買い物カゴ機能」の導入だ。昨年9月に開催された、EC事業者向けイベント「全国ECサミット2024」でも実装することが明かされていたが、まだ同一店舗において、複数のアイテムを一度に購入することはできない。
伝食の福地氏は「カート機能がないので、『同じ商品の2個セット』『3個セット』というように、わざわざセット商品のページを作らなければいけない。ユーザーから『まとめ買いがしたい』という要望があるたびに、商品ページを作っているので非常に手間がかかる」と明かす。
江川執行役員は「カート機能については、検討から開発の段階には移っている」と話す。ただ、『メルカリ』はもともと消費者同士で「1点もの」を売り買いするためのフリマアプリだ。一般的なB2CのECに特化した機能を、C2Cがメインであるアプリに装備するには、かなりの手間がかかるであろうことは想像に難くない。
メルカリShopsは「『メルカリ』の集客力」をバックとして、「メルカリの売上金の使い道に困っている」ユーザーのニーズを取り込むことで急成長を遂げた。ただ、C2CとB2Cがアプリ内で同居することの難しさもあるわけだ。買い物カゴや店舗内検索といった、他の仮想モールでは当たり前の機能がいまだに装備されていない。
江川執行役員は「機能が不十分なのにここまで成長できたわけで、大きなポテンシャルを感じる」と胸を張る。その一方で、B2C関連の機能を目立たせすぎると、フリマアプリである『メルカリ』の集客力や流通額にも影響が出かねない。こうした「ジレンマ」をいかに解決できるかが、今後の成長の大きな鍵になってきそうだ。
「質」確保も急務
もう一つの課題は出店者の「質」。ここ数年、EC業界で問題となっているのは、「自社では在庫を持たず、出店者がアマゾンなどで代理購入した商品を直接消費者に配送する」という「無在庫転売」だ。業界関係者からは、こうした転売業者がメルカリShopsで非常に目立っている、という声も出ていた。
江川執行役員は「手元に商品がない無在庫転売については、対策に力を入れている。また、出店審査に関しても、特に個人・個人事業主については審査を厳格化した」と、取り締まりを強化している点を強調。無在庫転売については禁止行為として定めるとともに、判明した場合は取引キャンセルや商品削除、利用制限を行う。また、無在庫転売であるかどうかにかかわらず、セラーの最大出品数についても上限を設けた(出店者によっては例外あり)。数万点を出店する無在庫転売業者は多いだけに、一定の成果は出ているようだ。
C2Cも含めて「安心・安全」ではない取引が俎上に上がることが多い『メルカリ』。それだけに、メルカリShops出店者の「質」確保は、今後の大きな課題となりそうだ。
江川嗣政執行役員に聞く
「次世代EC見据える」
カート・SKUの要望多く

メルカリShopsを統括する、江川嗣政執行役員VP of Shops/Ads(=写真)に今後の戦略などを聞いた。
◇
――メルカリShopsを、小規模事業者向けサービスから一般的な仮想モールへと転換した理由は。
「小規模事業者が出品する商品は、一般ユーザーが出品する商品の中に埋もれてしまいがちだった。その一方で、1つの店舗がたくさん出品すると、インプレッションは増えていく。たくさんの商品を販売できる事業者となれば、必然的に大手EC企業が向いているということになる。実際に、テストとして大手EC企業に出店してもらったところ、良い結果が出たので、現在の方針へと転換した」
――ただ、大手EC企業の商品が「メルカリ」に増えると、C2Cとのバランスが崩れる恐れもある。
「多面的にデータを見ながら、C2CとB2Cのバランスを考えている。とはいえ、一番大事なのは、出品者と購入者が満足すること。特に購入者にとっては、C2CやB2Cは関係なく、欲しい商品が見つかることが一番だろう。こうした観点を大切にしながらバランスを取っている」
――検索連動型広告について、店舗からの声は。
「費用対効果については好評。ただ、カテゴリーによってバラつきは出ているようだ」
――それ以外の広告は導入しないのか。
「オファーウォールを入れたリワード広告はテストとして導入している。また、『メルペイ』においては、外部EC事業者の商品を紹介するポイントモールの立ち上げを検討している。さらに、アフィリエイトプログラムとして『メルカリアンバサダー』という制度があるので、楽天市場の『ROOM』のようなサービスも可能ではないか」
――出店者からの機能開発の要望は出ているか。
「たくさんある。一番多いのはカート機能、次はSKU関連だ。ただ、中長期的に開発しなければいけないものもあれば、すぐにできるものもある。『売るための機能』でいうと、直近のキャンペーンにおける成果も踏まえて、要望と照らし合わせながら進めている」
――メルカリShopsに限定したセール企画などは検討しているか。
「検討段階ではあるが、C2CとB2Cの壁を超えて、『買い回り』のような企画ができれば、ユーザーにもっと楽しんでもらえるのではないかと思う」
――楽天やアマゾンなど他の仮想モールとの競合をどう捉えているか。
「そこまで強くは意識していない。それよりも『AIの進化でECがどうなるか』が大きなテーマだと思う。ECはパソコンから始まり、ガラケーによるモバイルECがあり、スマートフォンの進化でアプリを使ったECが主流となった。そして、SNSの発展は個人の情報発信力を高め、ユーザーの購買行動を変化させている。こうした『ソーシャルコマース』の隆盛は、われわれにとっても追い風だ。次のインフラチェンジは、やはりAI。AIを使うことでどれだけユーザーに喜んでもらえるか、出店店舗がどれだけ成長できるか、という部分は議論していかなければいけない。不足している機能を強化するのはもちろん、次世代ECを見据えていきたい」


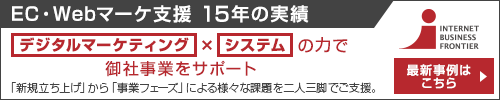

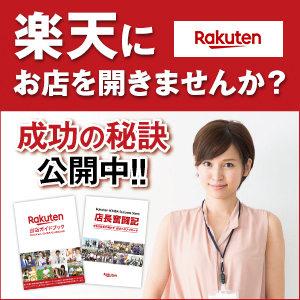
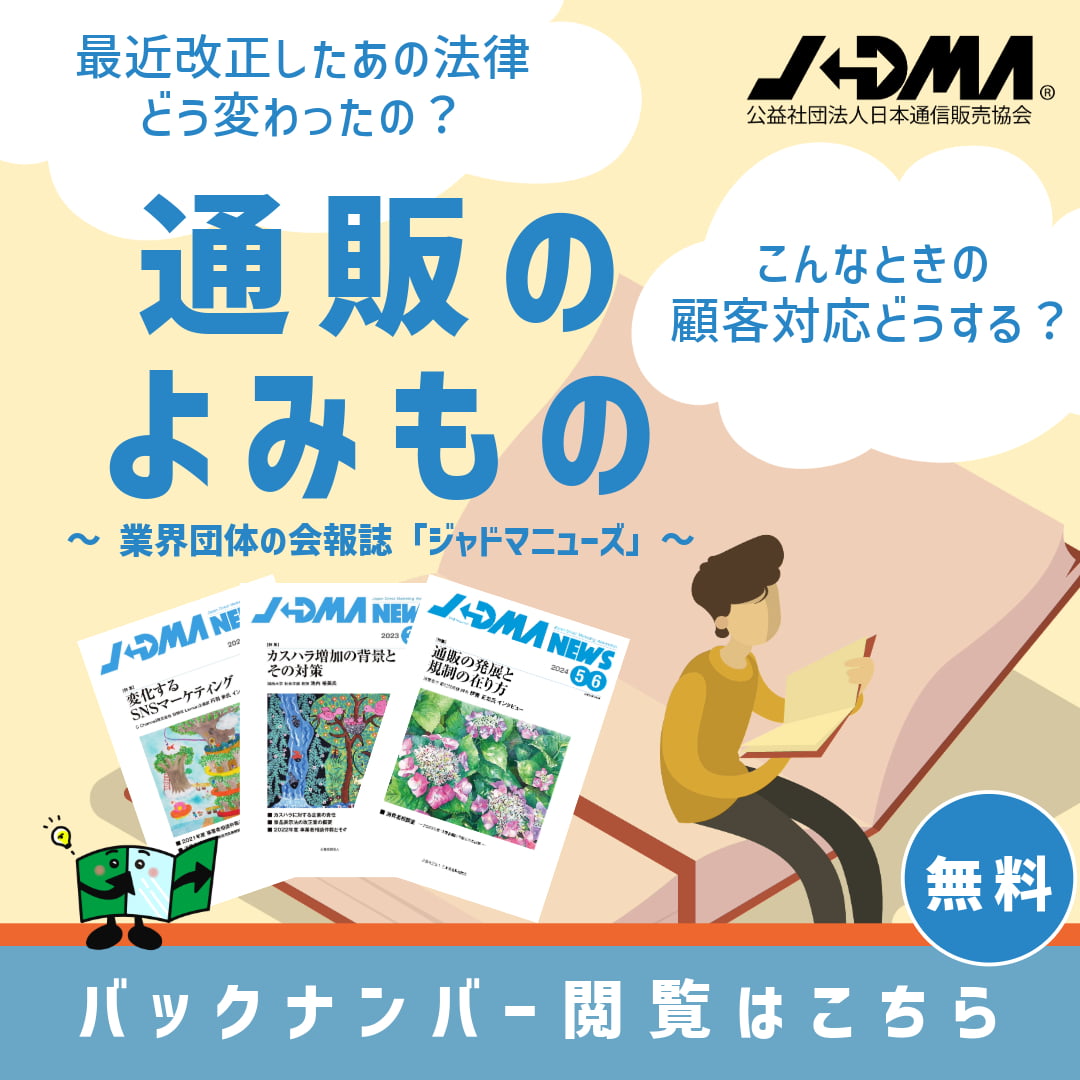





メルカリShopsは2021年のサービス開始当初、コロナ禍で苦しむ地域の生産者のための販路」という色合いが強く、クリエイターのハンドメイド作品や農家直送の野菜や果物、飲食店のグルメ、地方の特産品などの出品を想定していた。しかし、近年は機能的にも「仮想モール」へと近づくとともに、大手EC事業者も続々参入している。
出店以降、売り上げは順調に推移。メルカリShopsの優秀店舗を表彰する「メルカリShopsアワード2024」において、総合3位を受賞した。福地氏は「他の仮想モールはリピーターが70%程度を占めることが多いが、メルカリShopsの場合は新規がほぼ半数を占めている」と説明。売上金を使う目的ということもあるのか、安い商品を探しているユーザーが多い傾向にあるという。
メルカリShopsアワード2024では甲羅組以外にも、アイリスプラザや「いわゆるソフトドリンクのお店」のナカヱなど、楽天市場などでおなじみのEC企業が受賞。大手家電量販店のエディオンなど、EC専業以外の大手企業も。流通額が伸びているだけに、今後は大手企業のメルカリShopsへの出店は増えるものとみられる。
検索広告を開始
メルカリShopsを統括する、江川嗣政執行役員は「3月に(『メルカリ』としての買い物イベントである)『超メルカリ市』を開催したこともあり、もう一段階成長した感がある。出店者数も流通総額も順調に成長しており、EC事業者からの期待も実感できている」と近況を語る。
具体的な出店者数については公表していないが、法人出店に関しては2桁増のペースを維持しているという。「楽天市場などで活躍している上位店も増えているが、リユース大手の出店も目立つ」(江川執行役員、以下同)。直近では、漫画古書店のまんだらけが出店した。
メルカリShopsの場合、初期費用と月額費用が無料で、売れた場合のみ10%を支払う仕組みのため、他社の仮想モールよりも割安感があるのが特徴。加えて「メルカリ」自体の集客力が大きな魅力となる。
営業部隊に関しては、出店者を獲得するチームと、楽天でいう「ECコンサルタント」の役割を持つチームの2つに分かれる。出店者を獲得するチームに関しては、決済サービス「メルペイ」や単発アルバイト仲介サービス「メルカリ ハロ」などと同時に営業をかけるケースも増えている。さらには、「メルカリ」への広告出稿を提案、「メルカリ」の集客力を実感してもらってから出店してもらうケースもあるという。
直近の大きなトピックスは、昨年末の検索連動型広告導入だ。江川執行役員は「広告に関しては、他の仮想モールと大きな差があった部分。競合との差を埋めていくためのスタートを切ることができた」と話す。
現在、3桁の店舗が検索連動型広告を使っている。現状については「使っている店舗が増えれば増えるほど、クリック単価は上がっていくわけだが、まだ思ったほど高くなっていない。逆に、利用企業からみれば費用対効果は良いのではないか」。
広告商品は、検索画面の上から4番目に表示される仕組みだ。「『メルカリ』は元来C2Cマーケットなので、C2Cの商品を探しに来るユーザーが多いという仮説を立てた。そのため、上段はC2C商品にした方がユーザーにとっては良いのではないかと判断した」ためだ。もちろん、出稿する企業にとっては、1番上に表示されると効果が高いのは間違いない。メルカリでは、ユーザーが検索した際に表示する商品のマッチング精度を高めることで対応したい考えだ。
また、アプリの検索画面において、メルカリShopsを利用している法人が出品する商品を、それと判別することはできない。これについて、江川執行役員は「法人出品者を特別に目立たせることは考えていないが、信頼のおけるセラーを大切にしていきたいとは思っている。過去の取引実績や販売のボリューム、顧客とのトラブルはないかといった点を考慮し、『安心・安全』な出品者については検索アルゴリズムにある程度反映させたい」と説明する。
「カゴ導入」課題
現状、大きな宿題となっているのは「買い物カゴ機能」の導入だ。昨年9月に開催された、EC事業者向けイベント「全国ECサミット2024」でも実装することが明かされていたが、まだ同一店舗において、複数のアイテムを一度に購入することはできない。
伝食の福地氏は「カート機能がないので、『同じ商品の2個セット』『3個セット』というように、わざわざセット商品のページを作らなければいけない。ユーザーから『まとめ買いがしたい』という要望があるたびに、商品ページを作っているので非常に手間がかかる」と明かす。
江川執行役員は「カート機能については、検討から開発の段階には移っている」と話す。ただ、『メルカリ』はもともと消費者同士で「1点もの」を売り買いするためのフリマアプリだ。一般的なB2CのECに特化した機能を、C2Cがメインであるアプリに装備するには、かなりの手間がかかるであろうことは想像に難くない。
メルカリShopsは「『メルカリ』の集客力」をバックとして、「メルカリの売上金の使い道に困っている」ユーザーのニーズを取り込むことで急成長を遂げた。ただ、C2CとB2Cがアプリ内で同居することの難しさもあるわけだ。買い物カゴや店舗内検索といった、他の仮想モールでは当たり前の機能がいまだに装備されていない。
江川執行役員は「機能が不十分なのにここまで成長できたわけで、大きなポテンシャルを感じる」と胸を張る。その一方で、B2C関連の機能を目立たせすぎると、フリマアプリである『メルカリ』の集客力や流通額にも影響が出かねない。こうした「ジレンマ」をいかに解決できるかが、今後の成長の大きな鍵になってきそうだ。
「質」確保も急務
もう一つの課題は出店者の「質」。ここ数年、EC業界で問題となっているのは、「自社では在庫を持たず、出店者がアマゾンなどで代理購入した商品を直接消費者に配送する」という「無在庫転売」だ。業界関係者からは、こうした転売業者がメルカリShopsで非常に目立っている、という声も出ていた。
江川執行役員は「手元に商品がない無在庫転売については、対策に力を入れている。また、出店審査に関しても、特に個人・個人事業主については審査を厳格化した」と、取り締まりを強化している点を強調。無在庫転売については禁止行為として定めるとともに、判明した場合は取引キャンセルや商品削除、利用制限を行う。また、無在庫転売であるかどうかにかかわらず、セラーの最大出品数についても上限を設けた(出店者によっては例外あり)。数万点を出店する無在庫転売業者は多いだけに、一定の成果は出ているようだ。
C2Cも含めて「安心・安全」ではない取引が俎上に上がることが多い『メルカリ』。それだけに、メルカリShops出店者の「質」確保は、今後の大きな課題となりそうだ。
「次世代EC見据える」
カート・SKUの要望多く
――メルカリShopsを、小規模事業者向けサービスから一般的な仮想モールへと転換した理由は。
「小規模事業者が出品する商品は、一般ユーザーが出品する商品の中に埋もれてしまいがちだった。その一方で、1つの店舗がたくさん出品すると、インプレッションは増えていく。たくさんの商品を販売できる事業者となれば、必然的に大手EC企業が向いているということになる。実際に、テストとして大手EC企業に出店してもらったところ、良い結果が出たので、現在の方針へと転換した」
――ただ、大手EC企業の商品が「メルカリ」に増えると、C2Cとのバランスが崩れる恐れもある。
「多面的にデータを見ながら、C2CとB2Cのバランスを考えている。とはいえ、一番大事なのは、出品者と購入者が満足すること。特に購入者にとっては、C2CやB2Cは関係なく、欲しい商品が見つかることが一番だろう。こうした観点を大切にしながらバランスを取っている」
――検索連動型広告について、店舗からの声は。
「費用対効果については好評。ただ、カテゴリーによってバラつきは出ているようだ」
――それ以外の広告は導入しないのか。
「オファーウォールを入れたリワード広告はテストとして導入している。また、『メルペイ』においては、外部EC事業者の商品を紹介するポイントモールの立ち上げを検討している。さらに、アフィリエイトプログラムとして『メルカリアンバサダー』という制度があるので、楽天市場の『ROOM』のようなサービスも可能ではないか」
――出店者からの機能開発の要望は出ているか。
「たくさんある。一番多いのはカート機能、次はSKU関連だ。ただ、中長期的に開発しなければいけないものもあれば、すぐにできるものもある。『売るための機能』でいうと、直近のキャンペーンにおける成果も踏まえて、要望と照らし合わせながら進めている」
――メルカリShopsに限定したセール企画などは検討しているか。
「検討段階ではあるが、C2CとB2Cの壁を超えて、『買い回り』のような企画ができれば、ユーザーにもっと楽しんでもらえるのではないかと思う」
――楽天やアマゾンなど他の仮想モールとの競合をどう捉えているか。
「そこまで強くは意識していない。それよりも『AIの進化でECがどうなるか』が大きなテーマだと思う。ECはパソコンから始まり、ガラケーによるモバイルECがあり、スマートフォンの進化でアプリを使ったECが主流となった。そして、SNSの発展は個人の情報発信力を高め、ユーザーの購買行動を変化させている。こうした『ソーシャルコマース』の隆盛は、われわれにとっても追い風だ。次のインフラチェンジは、やはりAI。AIを使うことでどれだけユーザーに喜んでもらえるか、出店店舗がどれだけ成長できるか、という部分は議論していかなければいけない。不足している機能を強化するのはもちろん、次世代ECを見据えていきたい」