新着記事
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
2025年 4月17日 12:00
縮刷版購入者特典の通販新聞
全文記事検索サービス
年間購読のお申込み
人気記事ランキング
1
2025年 4月17日 12:00
2
2023年 7月20日 12:00
3
2025年 4月17日 12:00
4
2024年12月23日 12:00
5
2024年 3月22日 12:00
6
2025年 4月17日 12:00
7
2022年 6月23日 12:59
8
2025年 4月17日 12:00
9
2024年 9月19日 12:00
10
2024年 3月28日 12:00
1
2023年 8月24日 12:00
2
2025年 4月17日 12:00
3
2025年 4月17日 12:00
4
2025年 4月10日 12:00
5
2015年 9月 3日 14:35
6
2025年 4月17日 12:00
7
2025年 4月17日 12:00
8
2024年 9月19日 12:00
9
2024年12月23日 12:00
10
2024年 3月22日 12:00
1
2023年 8月24日 12:00
2
2025年 3月27日 12:00
3
2024年 9月19日 12:00
4
2025年 3月27日 12:00
5
2023年 7月20日 12:00
6
2024年 3月22日 12:00
7
2025年 4月 3日 12:00
8
2025年 4月10日 12:00
9
2024年12月23日 12:00
10
2025年 3月27日 12:00


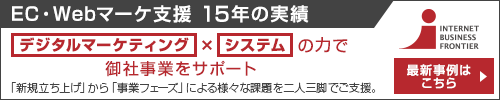

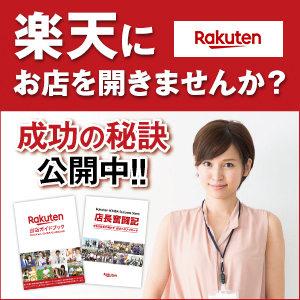
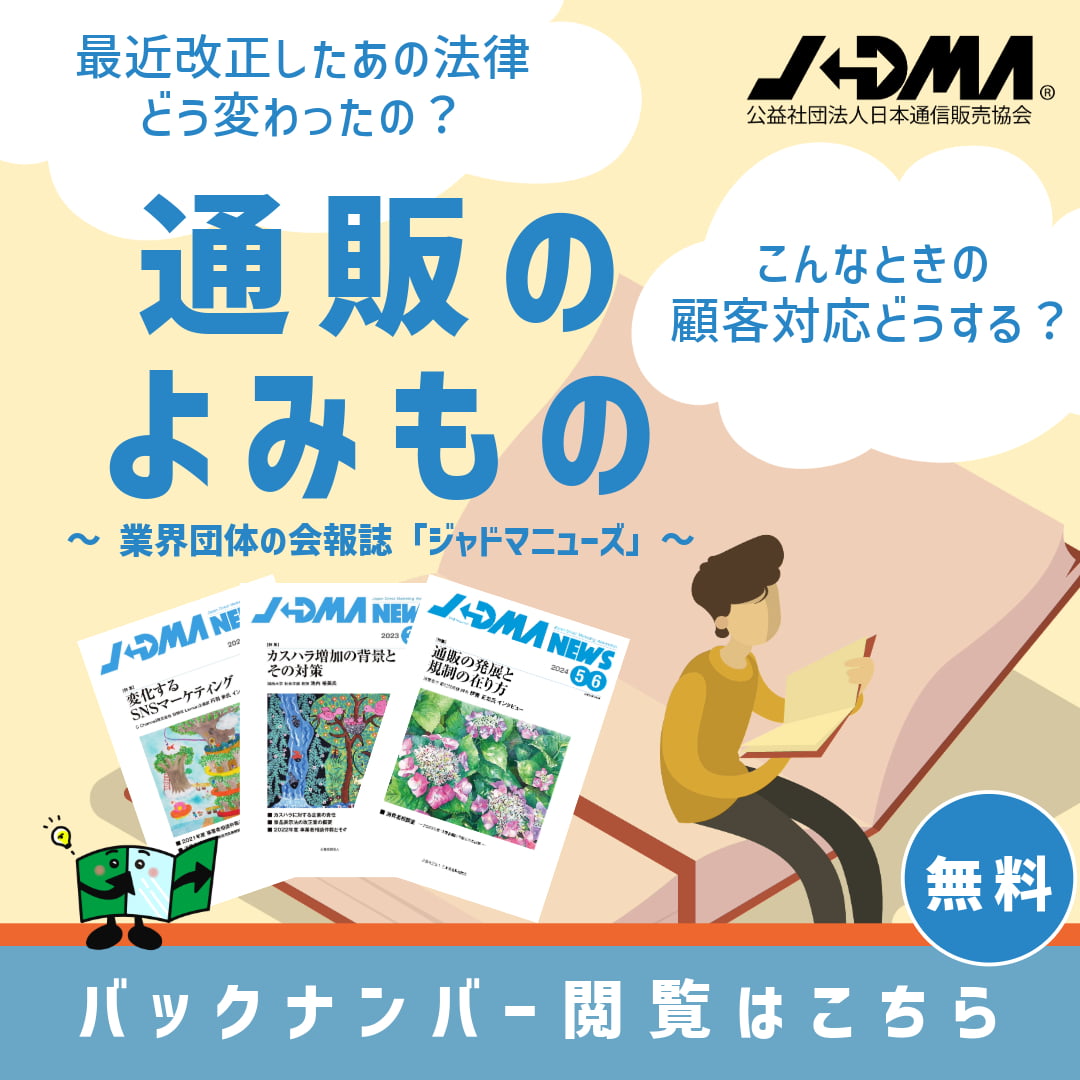





表示例は昨年10月、業界のあるセミナーで示された。特に注意されたのは、「限られた指標のデータを用い、全体に関する機能があると誤解を招く表示」。例えば、ドライアイに関する機能性表示をもって「目の健康に役立つ」など、目の健康全体に及ぶ表示がこれにあたる。ほかにも「関節機能の維持に役立つ」「記憶力をサポートする」といった表示例が示された。このため、企業は届出表示で「目の疲労感」「ピント調節機能の低下」など、評価結果から分かる複数の機能を具体的に示した上で、「○○の健康に」と届け出を行っている。
だが、具体的な表示例を示すことは、過去例からも規制につながる。今回のケースも、過去に厚生労働省が「さらさら」「ふしぶし」などの商品名62例を「効果を暗示するもの」として例示した「4・13事務連絡」と構図は同じだ。当時、改善指導を受けた事業者に加え、具体的な商品名を目の当たりにした周辺企業も商品名を変更する事態に陥った。具体的表示例を示すことは、こうして企業の萎縮を招く。
消費者庁は、「表示例だけを取り上げて良し悪しを論じるものではない」「すでに受理されたものの中にも『○○の健康に』といった表現はある」とする。だが、広告表示においては、一定の範囲で表示は省略されるのが通例。表示例に直面した事業者や媒体の考査担当者の中には、「『○○の健康に』という表現に注意する」という意識が生まれ、すでに萎縮効果を生んでいる。行政の執行担当官OBも「(省略が過ぎれば)指導対象になる」との見解を示す。
そもそも、表示例は健康の維持増進の範囲に限定される制度で「健康」をいう言葉を規制する自己矛盾を起こしている。「限られた指標」と「全体の健康」の差はどうすれば埋まるのか。消費者庁は「数ではない」と説明するが、事業者としては意識せざるを得ない。
制度は、企業が安全性や機能性の根拠を持ち、一定のルールのもと、自らの責任で表示をするものであるはずだ。表示に対する監視機能も「事後チェック」を前提としていた。だが、実際は届出内容を消費者庁がチェックし、「不備」を指摘、実質的な「審査」が行われている。制度を設計した消費者庁自身が公然と制度の根幹をないがしろにし、消費者庁の意向を意識せざるを得ない企業もこれを甘んじて受けざるをえない状況が生まれている。
制度の目的は、健康食品の表示解禁により消費者に分かりやすい表示を行い、商品選択の判断基準を示し、消費者教育につなげることだ。同時に、成長戦略としても期待されている。だが、不適切表示の例示により早くも骨抜きにされようとしている。まだ、制度の成否は明らかになっておらず、実際に経済活性化につながるか、重要な時期でもある。消費者庁は無用な混乱を招く「不適切な表示例」を撤回すべきだ。